日本証券金融グループでは、リスクアペタイト・フレームワーク(RAF)をコーポレートガバナンスの枠組みの一部と位置付け、「当グループの社会的役割および経営理念に基づき、経営体力の範囲内で中期経営計画達成のために進んで取るべきリスク*の種類と量(リスクアペタイト)、および回避すべきリスク**を明確にし、経営管理とリスク管理を一体的に行う枠組み」と定義しています。
当社のRAFは、金融商品取引法に基づく免許を受けて証券市場のインフラ機能を担う証券金融会社として求められる高い財務健全性の維持と上場企業として求められる中長期的な企業価値の向上の両立を主な目的とし、資本配分や収益力の強化を含むリスクテイク方針全般に関する検討・決定プロセスの透明性の向上、経営資源配分の最適化およびモニタリング体制の強化を図るものです。
*収益を生み出す活動に付随して発生するリスク
**コンダクトリスク等、当社として許容しないリスク

当社のRAFの運営では、証券市場のインフラ機能を担う当社が果たすべき社会的役割や当社の中長期的な将来像を踏まえ、取締役会が経営全体としてのリスク管理方針を定めるとともに、中期経営計画と整合的に、リスクアペタイトおよびそれらを具体的に表すリスクアペタイト指標などRAFの基本事項を決定します。リスクアペタイトは、経営の安定性・財務の健全性の観点のほかインフラ機能を担う社会的責任や証券市場への貢献など幅広い観点から設定しています。
経営の業務執行においては、取締役会で決定されたリスク管理方針、リスクアペタイトおよびリスクアペタイト指標を念頭に、業務ごとにより詳細な目標値と業務計画等を定め、中期経営計画を推進します。
取締役会は、リスクアペタイトおよびリスクアペタイト指標のモニタリング等を通じて業務執行状況を監督しており、リスクアペタイト指標が設定した水準から乖離した場合には、要因を分析のうえ対応策を策定・実行するなど、継続的にRAFの実効性改善・強化を図っています。
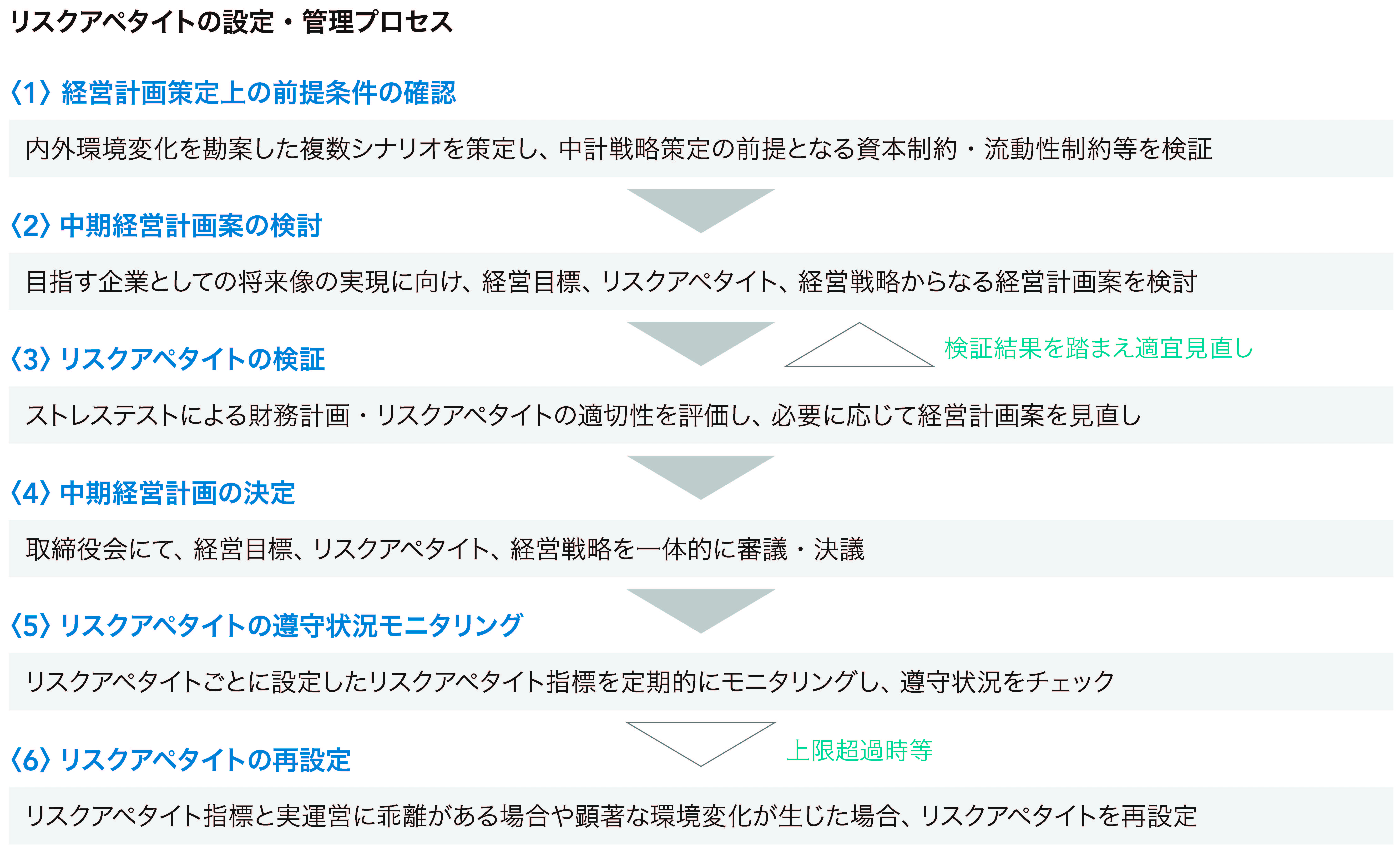
当社は、証券市場におけるインフラの担い手としての公共的役割を果たすため、リスクテイクにあたっては、当社の財務健全性が維持可能であること、またセキュリティファイナンス業務等の兼業業務については、免許業務である貸借取引業務の安定運営に影響がないことを強く意識しています。また、定期的な研修や面談等の実施を通じて、従業員のコンプライアンス意識や業務環境の実態把握に努めコンダクトリスクの低減にも留意しています。
こうした当社のアイデンティティから醸成されたリスクカルチャーは、「役職員の行動規準」および「リスクの管理方針」により、社内にしっかりと浸透しRAFの運営基盤となっています。また、RAFの運営を通じてリスクカルチャーが継続的に意識され、さらに醸成・浸透が深まるという循環的作用を通じて、リスクガバナンスは一層強固なものとなります。
当社は、コーポレートガバナンスの一部を構成するリスクガバナンスについて、今後もさらなる高度化を推進し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。
当社では、想定されるリスクを信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク、およびシステムリスクに大別し、これらを管理対象としています。このうち信用リスクおよび市場リスクについては、リスクを定量的に把握し、経営体力に見合う適切なレベルにリスクをコントロール(統合リスク管理)しながら収益の確保に努めています。一方、流動性リスク、オペレーショナルリスクおよびシステムリスクについては、リスクの特性に応じた適切な管理を実施することにより、リスク発生の未然防止に努めています。
レポーティングについては、信用リスクおよび市場リスクについてはリスク管理委員会で、流動性リスクについてはALM 委員会での各審議を通じて、経営会議に報告されます。各委員会の担当役員は、定期的にリスクの状況やリスク管理高度化施策などを取締役会に報告しています。
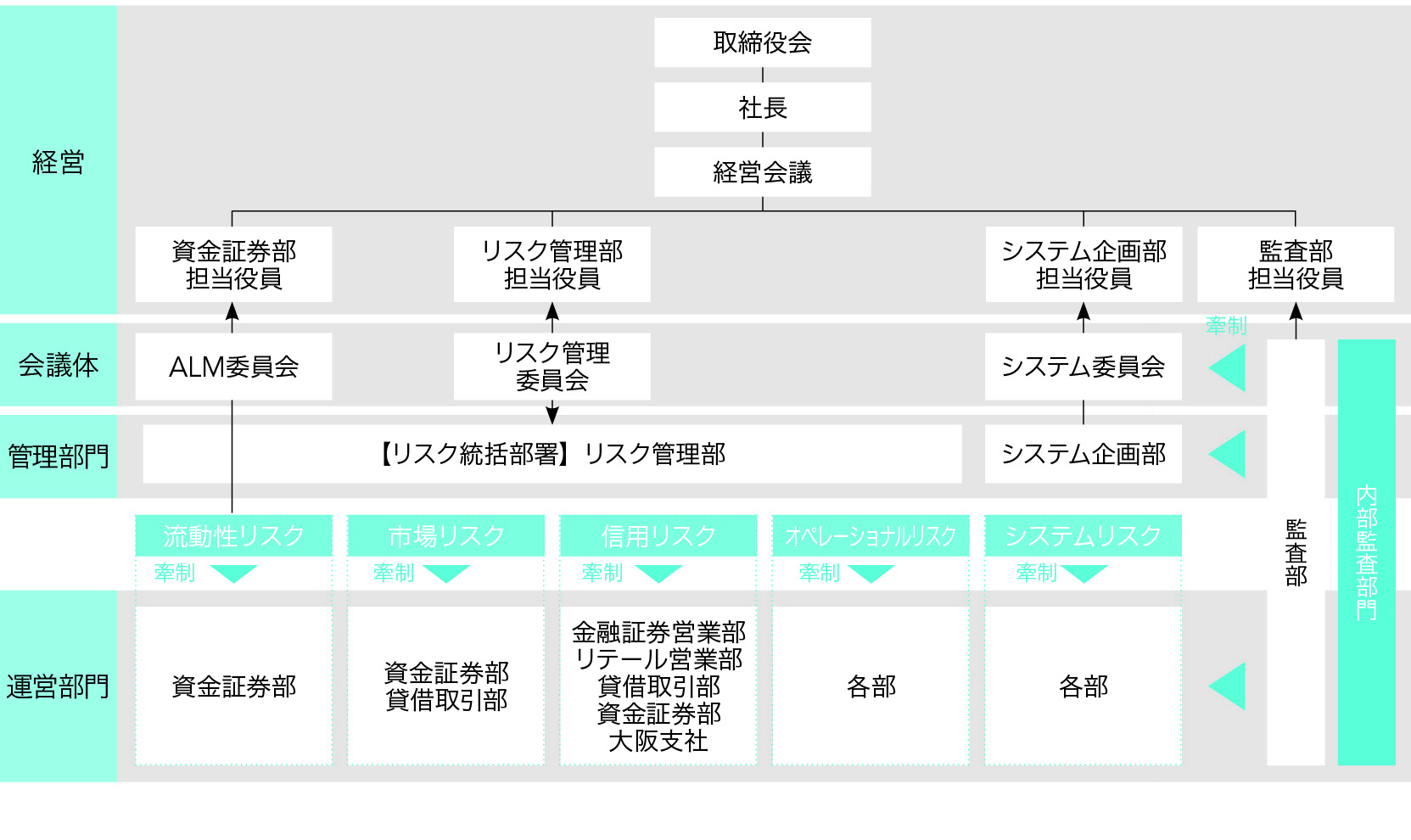
リスクアペタイト・フレームワークを活用した具体的なリスク管理態勢については、以下記載のとおり整備しています。
当社はJSCCの清算・決済制度や日銀のオペレーションへの参加にあたり、金融商品取引法に準じた自己資本規制比率を算出・管理し、これを一定水準以上に維持することが求められています。具体的には、月次で当該比率を精緻に算出・管理するとともに、日々の市場変動に伴う自己資本への影響をモニタリングし、機動的に経営に報告しています。
また、ストレステストによる自己資本へのインパクトを試算することで自己資本充実度の検証を行い、必要に応じてアクションプランを策定しています。ストレステストとしては、月次での信用・市場の各個別ストレスシナリオに基づく定点チェックと、半期次での足元の金融環境を踏まえたシナリオに基づく包括的なストレステストの二種類を実施しています。
各種リスクを統一的な手法により計量化し、リスクの総量が経営体力の範囲内に収まるよう管理する手法を統合リスク管理といいます。
当社では、信用リスクおよび市場リスクの各リスクについて、自己資本の範囲内でリスク資本の配賦を行ったうえで、VaR(バリュー・アット・リスク)の手法により計量化し、算出したリスク量を配賦されたリスク資本の範囲内で管理する手法を導入しています。
また、オペレーショナルリスクについても基礎的な手法により計量化し、これに対応するリスク資本必要額を設定しています。
リスク資本の配賦額は、年度末に開催する定例の「リスク管理委員会」で事前審議のうえ、経営会議において最終的に決定しています。各リスク運営部門は、配賦されたリスク資本の範囲内でリスクをコントロールし、これら部門から独立したリスク管理部が計量化して、リスクの運営状況をモニタリングし、役員へ報告しています。リスクが配賦されたリスク資本の額を上回るおそれが生じた場合は、臨時に「リスク管理委員会」を開催して対応方針を審議したうえで、経営会議に諮ることとしています。
※VaRとは、保有資産が、一定期間(保有期間)、一定確率(信頼水準)の下で被る可能性のある予想最大損失額のことで、過去のデータに基づき統計的手法により算出します。当社では、信頼水準99%、保有期間10日~1年を前提としてVaRを算出しています。
当社では、社内格付による取引先の評価を行うとともに、社内格付別のデフォルト率を用いて信用リスクの計量化および管理を実施しています。
与信管理面では、取引先・受入担保銘柄・貸付案件の審査を行うとともに、取引先別の取引限度額の設定・管理を行っています。個々の貸付業務については、原則として貸付額に相当する有価証券をそのボラティリティや市場流動性等に応じた適切なヘアカット(掛目)を設定したうえで受け入れるとともに、担保有価証券を日々値洗いすることでエクスポージャーの発生を抑制しています。また、貸付先が破綻した場合には担保有価証券の売却などにより迅速に債権を回収できる態勢を整えるとともに、各業務部門が所管する資産について厳密な自己査定を実施しています。そのほか、大口与信管理として、業務横断での取引先別にストレス時を想定したエクスポージャーを日次で算出し、一定の限度内に収まっていることを日次でモニタリングすることで特定の取引先に対する過度なエクスポージャーの発生を抑制しています。
当社では、市場リスクの計量化(ヒストリカル法または分散共分散法)および管理を実施しています。
また、当社が採用している市場リスク計量化モデルの信頼性を検証するため、算出したVaRとポートフォリオを固定した仮想損益を比較するバックテスティングも行っています。一方、投資損益に対しては、総合損益ベースでの損失枠などを設定することで、適切な投資損失管理を行っています。
当社では、流動性リスクを重要なリスクとして認識し、複数の金融機関からのコミットメントラインの取得や調達手段の多様化および調達期間の分散化を図りながら、業務の安定運営に必要な資金流動性の確保に努めています。
資金繰り管理面では、金融市場において一定のストレス事象が発生するとの想定のもとで流動性余力の最低維持額を設定し、資金繰り見通しの策定、調達可能額や高流動性資産保有状況の把握、大口資金の期日集中の確認などにより、流動性余力の状況をモニタリングするとともに、日々の資金繰り状況について経営陣に報告する体制を整備しています。さらに、資金調達環境にストレスが発生した際の資金流出など想定したストレステストの実施により、手元流動性の所要水準の確認・把握を行っております。
また、日証金信託銀行から資金繰り見通し等の報告を日次で受け、同社の流動性余力の把握をするなど、連結ベースでの流動性リスク管理を行っています。そのうえで、不測の事態に備え、即時に資金化が可能な国債を一定量保有するなどの流動性補完措置を講じています。
当社では、各部がオペレーショナルリスクの管理を所管しており、オペレーショナルリスクの軽減を図るため、規程・マニュアル等の整備および研修等を通じて、職員に対して正確な事務取扱いを周知徹底しています。また、自主検査を定期的に実施することにより、事故の未然防止および事務処理体制の改善に努めています。
当社では、情報セキュリティ対策の基本方針として、情報セキュリティ管理方針を定め、システム企画部がシステムリスクの管理を所管し、各リスクに対し必要な施策を推進しています。情報システムについては、安定稼動に万全を期すべく、ネットワーク・機器類の二重化等によりシステム障害発生の未然防止に努め、システム開発・運用面では、これを安全かつ効率的に行うため、作業手順を明確化するとともに監視体制を整備しています。
また、当社の保有する情報資産(情報および情報システム)の保護については、不正アクセスやサイバーセキュリティ対策を講じているほか、役職員が遵守すべき規程等を整備し、その取扱いを役職員に周知徹底しています。さらに、システム障害発生時の影響を最小限に抑え、速やかに復旧するため、各種対応マニュアルの整備、訓練の実施等の措置を講じています。